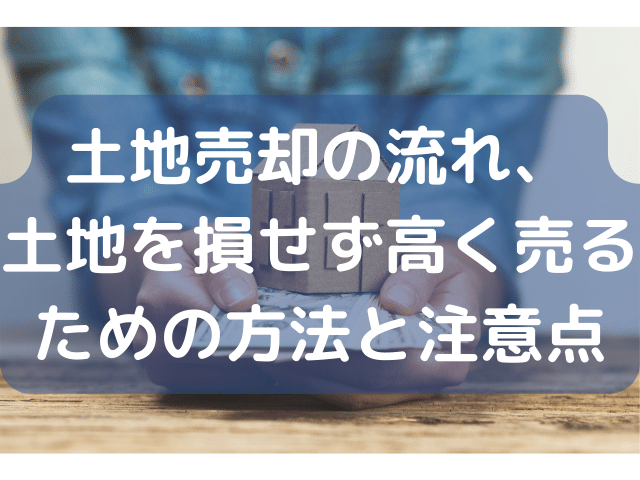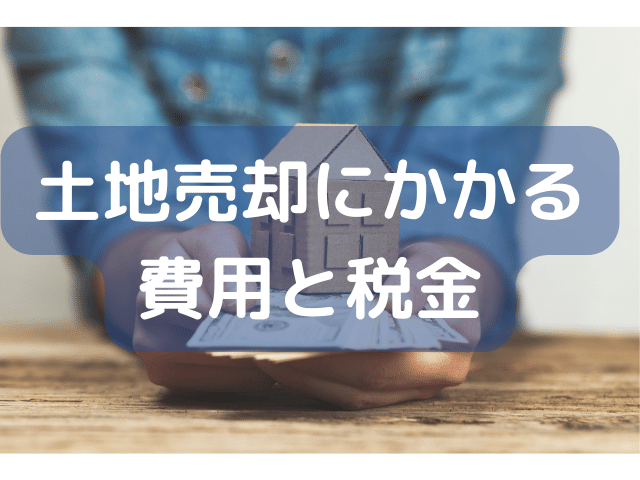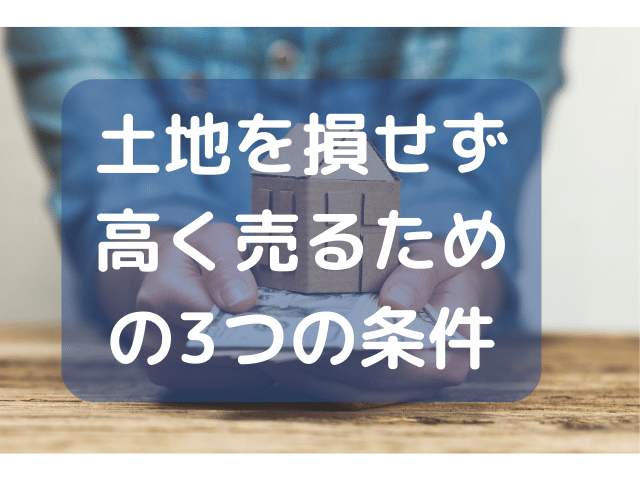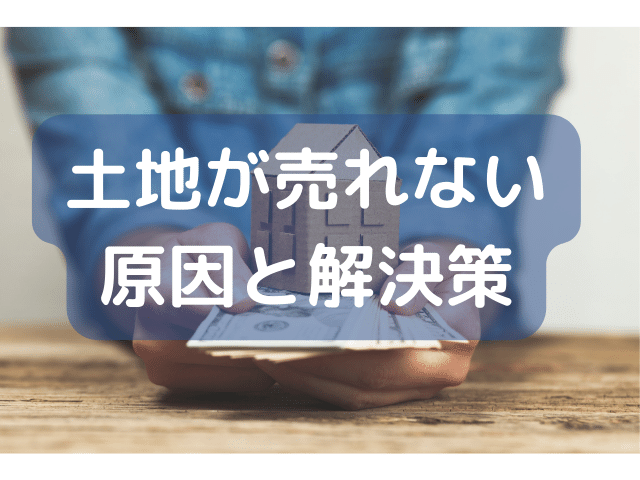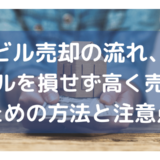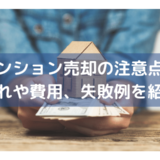この度、ご自身が所有する土地の売却について、どのような手順を踏んで進行すれば良いのかを説明する項目を準備しました。
一般的には、土地を売却したいと考えたときに、その具体的な進め方が分からずに迷われる方が多いと聞きます。
そこで今回は、そういった疑問を解消すべく、土地売却に関する全過程を、その各ステップごとに丁寧に分けて説明して参ります。
また、それと同時に、土地を売却する際の注意点や有益なアドバイスも一緒にご紹介いたします。
土地売却の大まかな流れとしては、大きく分けて「売却に至るまでの準備段階」「実際の売却進行の中心部分」「売却完了から引き渡しまでの後処理」の3つのステップを進んでいくことが求められます。
まず最初に、準備段階にあたる部分では、売却をスムーズに進めるための準備を進行していきます。
その後、売却中の中心部分で実際の取引が行われ、最後に、引き渡し完了までの後処理で納得いく売却が完了となります。
これらのステップを一つ一つ丁寧に踏んでいくことで、売却の全過程を理想的に進めることができるでしょう。
<概要>
土地売却の流れは以下の6つのステップで行われます。
1. 土地を売却する前の事前準備として、希望条件の整理、相場の確認、境界線の確認を行います。
2. 準備が整ったら不動産会社に査定を依頼し、媒介契約を締結します。
3. 売り出し価格を設定して販売活動をスタートさせ、売主の準備も行います。
4. 売買契約当日の手続きと手付金について確認し、手付金の残り金額を支払います。
5. 土地の引渡し時に手付金の残り金額が支払われ、所有権が買主に移ります。
6. 土地を売却した後は翌年に確定申告を行い、所得税及び住民税を納税します。
節税特例を利用することもできます。
このように、土地売却は様々な手続きと準備が必要ですが、スムーズに進めるためにはしっかりと準備を行い、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
土地売却の流れ6ステップ
①土地を売却する前の事前準備として、希望条件の整理、相場の確認、境界線の確認を行いましょう
土地を売却する前には、いくつかの事前準備が必要です。
まずは、希望条件を整理しましょう。
ローンの残債がある場合は、残りのローンの額を確認しましょう。
さらに、いつまでに土地を売却したいのか、どのくらいの売り出し価格を希望しているのかも考えておきましょう。
次に、土地の相場を確認します。
相場を把握することで、売り出し価格を適切に設定することができます。
同じくらいの広さや周辺環境を持つ土地の売り出し価格を調べることをおすすめします。
そして、土地の境界線も確認しておきましょう。
土地を売買する際は、自分の土地の境界を明確にする必要があります。
境界線がはっきりしていないと、隣地の所有者とのトラブルの原因になる可能性があるからです。
境界線を明示するためには、隣接地との境界線を確定するのが最も確実です。
確定測量図や地積測量図を用意することで、境界線を明確にすることができます。
ただし、古い地積測量図は境界線が確定されていないことが多いため、売却する際は確定測量図を用意することが望ましいです。
もし手元に確定測量図がない場合は、早めに土地家屋調査士に依頼し、図面を作成しておくことをおすすめします。
さらに、売却には他の書類も必要になります。
身分証明書や実印、印鑑証明書、登記権利書や登記識別情報通知、固定資産税評価証明書や固定資産税納税通知書などが必要です。
土地が相続された場合は、所有者の名義を明確にするために、売却前に登記簿謄本の名義変更が必要です。
②準備が整い次第、不動産会社に査定を依頼しましょう
不動産の売却を考えている方にとって、まず行うべきは不動産の査定です。
不動産査定には、簡易査定と訪問査定の2種類がありますが、売却の意思が固まっているのであれば、より精度の高い訪問査定をおすすめします。
訪問査定では、実際に不動産の現地を担当者が訪れ、敷地の形状や境界線、越境の有無、高低差、周辺環境、残置物の有無などを詳細に調査します。
この調査には通常、1週間前後の時間がかかりますが、それだけ正確な査定結果が得られるのです。
査定価格が提示されたら、その額だけで不動産会社を選んではいけません。
まずは、
「あなたが頼んだ査定価格を決定した基礎となる要素に関して、適切で理解できるような説明が示されたかどうか」
「査定を進行する過程で、査定員があなたの状況や要望にしっかりと耳を傾け、心からのサポートを提供してくれたかどうか」
「その業者がこれまでに多くの案件を取り扱ってきた経験が豊富で、信頼できるかどうか」
といった多角的な観点で不動産会社を見極めましょう。
そして、納得のいく不動産会社と媒介契約を締結します。
媒介契約とは、売却を仲介してもらう不動産会社と結ぶ契約のことです。
専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類がありますので、自分に合った契約形態を選びましょう。
売却は大きな決断ですので、不動産査定から媒介契約まで、慎重に進めてください。
信頼できる不動産会社とのスムーズな取引が実現できれば、満足のいく売却ができることでしょう。
③売り出し価格を設定して販売活動スタート!売主の準備も重要
不動産会社と媒介契約を結んだ後、売り出し価格を決定します。
不動産会社が査定した価格を基に売主が設定します。
売り出し価格が決まったら、販売活動がスタートします。
売り出し価格は、不動産会社と相談しながら決定しますが、査定価格を基本として考えてください。
不動産会社は市場情報や類似物件の売却事例を参考にして査定を行います。
査定価格は売却の目安ですが、売主が希望する価格に応じて調整することも可能です。
売り出し価格を設定する際には、現状の不動産市場や近隣の相場価格を把握することが重要です。
市場が活発で需要が高い場合は、査定価格よりも高い価格を設定することができますが、市場が冷え込んでいる場合は査定価格よりも低い価格を設定する必要があります。
また、販売活動がスタートする際には、不動産会社が購入希望者を募るための広告やPR活動を行います。
これによって多くの人に物件の情報を知ってもらい、見学に訪れる人数を増やすことができます。
売主も土地の手入れをしっかり行い、見栄えの良い状態にしておくことが重要です。
特に雑草の生えたままであったり、不要な物が散乱していると物件の魅力を損なうことになります。
可能な限り整理整頓を行い、土地をきれいに保つように心がけましょう。
以上のような準備を行うことで、売り出し価格を設定し販売活動をスタートさせることができます。
売主と不動産会社が協力して、可能な限り多くの人に物件の魅力を伝えていきましょう。
④売買契約当日の手続きと手付金について
売買契約が成立すると、契約書の説明を行う不動産会社と買主の間で売買契約に関する重要事項を確認します。
一方、売主は契約書の内容を事前に確認しておくことが大切です。
契約当日、買主と売主は契約書に記名・捺印することになります。
この手続きが完了すると、買主は売主へ手付金を支払います。
手付金は、買主または売主が契約に違反した場合の違約金としての役割を果たします。
買主は手付金放棄により、売主は手付金を返還し、さらに同額の金額を追加で支払うことで、契約を解除することができます。
この追加の支払いを「倍返し」と呼びます。
手付金は、買主と売主の双方にとって重要な要素であり、契約の履行を保証する役割を果たします。
売主は手付金を確実に受け取ることで、買主の真剣度を確認し、取引の安定性を確保することができます。
一方、買主は手付金を支払うことで、取引を確定させる意思を示すことができます。
手付金は、売主に対する責任を持ち、契約を守ることを約束するものとなります。
売買契約当日の手続きと手付金の取り扱いは、不動産取引において非常に重要です。
売主も買主も、契約前に契約書の内容をしっかりと確認し、手付金の取り扱いについて理解しておくことが大切です。
適切な手続きと取引条件の確認により、円滑な不動産取引を進めることができます。
⑤土地の引渡し時に支払われる手付金の残り金額について
土地の売買契約を行った後に支払われる手付金の残り金額についてご説明いたします。
一般的な流れでは、土地の引渡しの日に手付金の残り金額が支払われます。
この際、売主は必要な書類を買主に渡すことが求められます。
また、もし買主が住宅ローンを利用する場合は、引渡しの決済は金融機関で行われることがほとんどです。
具体的な流れは以下のようになります。
まず、買主は金融機関にて住宅ローンの手続きを行います。
ローンの審査や必要書類の提出などの手続きを済ませていただきます。
その後、引渡しの日になると、金融機関から必要な支払いが行われます。
つまり、買主がローンの手続きを済ませた後、金融機関から売主へ残りの金額が支払われます。
この支払いにより、引渡しの手続きが完了し、土地の所有権が買主に移ります。
このように、一般的な流れでは土地の引渡し時に手付金の残り金額が支払われることになります。
しかし、具体的な支払いの方法や手続きは契約内容や金融機関の条件によって異なる場合もありますので、注意が必要です。
契約前にしっかりと確認を行い、スムーズな引渡しを行うようにしましょう。
⑥土地を売却したら、翌年には確定申告を行いましょう
土地を売却した場合、翌年には必ず確定申告を行う必要があります。
この時、得た譲渡所得に基づいて所得税及び住民税を納税することになります。
ただし、一定の条件を満たす場合には、節税特例を利用することができ、確定申告を行うことで税金を節約することができます。
確定申告をする際には、売却にかかった費用を経費として計上することができます。
具体的には、測量費や解体費用、仲介手数料などが含まれます。
したがって、これらの費用に関する領収書はしっかりと取っておくようにしましょう。
これによって、売却にかかった費用を所得から差し引いた金額を算出し、納税額を軽減することができます。
また、節税特例を利用することでさらに納税額を抑えることもできます。
具体的な節税特例には、固定資産税・都市計画税の還付や、特定資産売却損の繰り越しなどがあります。
これらの特例を活用することで、より効果的な節税が可能です。
しかし、確定申告は複雑な手続きであり、専門的な知識が必要です。
そのため、税理士や税務署の相談窓口などに相談することをおすすめします。
専門家のアドバイスを受けながら、最適な節税方法を選ぶことが重要です。
いずれにしても、土地の売却に伴う確定申告は避けては通れないものです。
納税額を最小限に抑えるためにも、正確な情報を基にした確定申告を行うことが重要です。
土地売却にかかる費用と税金
土地売却にかかる諸費用の目安
土地を売却する際には、いくつかの諸費用がかかります。
ここでは、その目安をご説明します。
解体費用
建物が建っている場合、取り壊し費用がかかります。
木造なら3万~5万円/坪、鉄骨造なら4万~6万円/坪、鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造なら6万~8万円/坪などが目安となります。
このように具体的な費用は建物の大きさや構造によって変動します。
測量費用
土地の地積測量図や境界確認書面の作成には、土地家屋調査士に支払う費用がかかります。
一般的には、40万~100万円程度となります。
土地の地積や形状によっても費用は異なるため、具体的な見積もりを取りましょう。
仲介手数料
土地を売却する場合、不動産会社を通じて取引を行うことが多いです。
その際には、仲介手数料が発生します。
手数料の評価方法にはいくつかありますが、一般的には取引物件価格の3%に加えて6万円+消費税がかかります。
ただし、取引額が400万円を超える場合は、上限が法的に定められており「取引物件価格×3%+6万円+消費税」以上の手数料は請求されません。
繰り上げ返済手数料
もし土地に残っている住宅ローンがある場合、一括で返済する際に繰り上げ返済手数料が発生することがあります。
この手数料は金融機関に支払うもので、一般的には5千円から3万円程度です。
ただし、具体的な手数料額は金融機関の規定によって異なるため、事前に確認をしておきましょう。
以上が土地を売却する際にかかる諸費用の目安です。
具体的な費用は、土地の状況や契約書によって異なる場合がありますので、専門家に相談して詳細を確認することをおすすめします。
土地を売却する際にかかる税金とは?
土地を売却する際には、売却時と売却後に様々な税金がかかります。
まず、売却契約書には土地の価格に応じて1万円から6万円程度の印紙税が必要です。
これは、売買契約書に印紙を貼って納税することになります。
また、もし土地に抵当権が付いている場合には、抵当権抹消の登録免許税が発生します。
抵当権を抹消するためには、不動産1件につき1000円の登録免許税が必要となります。
これは、ローンの完済などで抵当権を消す際に支払う税金です。
さらに、土地を売却して利益が出た場合には、その利益に対して譲渡所得税と住民税が課されます。
売却益の20%から40%程度が譲渡所得税として課税されます。
ただし、この税率は売却時点から所有していた期間によって異なります。
所有期間が5年を超える場合、長期譲渡所得として所得税と住民税が課されます。
この場合の税率は20.315%です。
一方、所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得とされ、税率は39.63%になります。
つまり、土地を売却するタイミングで所有期間によって税率が大きく異なることに注意が必要です。
したがって、土地を売却する際には売却時に印紙税や抵当権抹消の登録免許税を納税する必要があります。
さらに、売却によって利益が出た場合には譲渡所得税と住民税も支払う必要があります。
税金の計算や手続きについては、専門家に相談しましょう。
3000万円の特別控除を利用して不動産の売却税金を節約しよう!
不動産の売却には、上記の通り譲渡所得税がかかります。しかし、特定の条件を満たす場合、最大で3000万円まで譲渡所得から控除される特別控除を受けることができます。
特別控除を受けるためには、まずマイホームの売却をしなければなりません。
土地のみの売却には適用されないので、注意が必要です。
また、売却する不動産の所有期間も重要な要素です。
土地と建物の所有期間が10年を超える場合には、「10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」との併用も可能です。
特別控除のメリットは、譲渡所得税の軽減です。
最大で3000万円まで控除されるため、税金負担が大幅に軽くなります。
これにより、不動産の売却に伴う税金負担を少なくすることができます。
特別控除を受けるためには、所定の申告書を提出する必要があります。
不動産の売却手続きと同時に、税務署への申告を行いましょう。
また、条件を満たしているかどうかは個別の場合により異なるため、事前に税務署や税理士に相談することをおすすめします。
是非、特別控除の活用を検討してみてください。
相続した空き家を売却すると、特別控除を受けることができる!
相続した空き家を売却する際、受けられる特別控除として「相続空き家の3000万円特別控除」があります。
この特別控除では、要件を満たしている場合に譲渡所得から最大3000万円が控除されることができます。
要件を確認して、節税効果を最大限に活用しましょう。
控除を受けるためには、売却額や所有期間などの条件を満たす必要がありますので、事前に十分な情報収集を行いましょう。
配偶者控除には注意!
不動産を売却する際には、成約価格によって配偶者控除の対象から外れる可能性があります。
配偶者控除は、扶養に入っている配偶者がいる納税者に対して一定の所得控除が行われる制度です。
売却により所得が増えてしまう場合、配偶者控除の範囲外になることがありますので、事前に自分の状況を確認しておくことが重要です。
特例の詳細な内容や要件については、国税庁のホームページ「マイホームを売ったときの特例」で調べることができます。
ただし、税金に関することは複雑なため、大きな金額がかかわる場合は税理士など専門家に相談することをおすすめします。
的確なアドバイスや助言を受けることで、より効果的な節税が可能です。
売却に伴う控除についてしっかりと理解し、計画的に進めましょう。
土地売却のパターンと注意点
古家付き土地の売却には2つの方法がある
古い一戸建てを含む土地を売却する際には、古家付き土地のまま売却する方法と、更地にして売却する方法の2つが選択肢となります。
古家付き土地のまま売却する方法
古家付き土地のまま売却する方法では、固定資産税が抑えられるメリットがあります。
古家が建っている場合には、減税措置が適用され、土地分の固定資産税を抑えたまま売却することが可能です。
ただし、この方法では売却に時間がかかることがある一方、減税措置が適用されるため、結果的にコストを抑えることができるかもしれません。
また、古家付き土地の売却では、売主は解体費用を負担する必要がありません。
一般的に木造一戸建ての解体費用は3万~5万円/坪かかるため、これを負担する必要がないのは大きな利点です。
ただし、買主が古い家を建て替えたい場合には、古家付き土地だと買主が家を解体する必要があるため、買い手が付きにくい場合があります。
さらに、解体費用分の値引きを求められる可能性もあるでしょう。
また、売却が進まずに長期間空き家になると、管理費がかかるだけでなく、建物の倒壊や治安の悪化といった問題も生じる可能性があるため、注意が必要です。
古家付き土地の売却方法を選ぶ際には、売主と買主のニーズや条件を考慮し、最善の方法を選ぶことが重要です。
売主がスムーズに売却できるよう、様々な要素を考慮しながら進めることがポイントです。
更地にして売却する場合
更地にして売却する場合は、建物を取り壊し、土地を更地にして売る方法です。
更地の土地の場合は、相場価格で売却できる可能性が高まります。
買主がすぐに家を建てられる状態なので、売却しやすいのです。
そのため、売却期間は古家付き土地に比べて短くなるのが一般的です。
更地の土地では、売れるまでの間、駐車場として土地を活用することもできます。
この場合、土地の運用利益で固定資産税の負担を軽減できるメリットがあります。
ただし、特例控除を利用する予定がある場合には、土地を貸すことで特例控除を利用できなくなる点には注意が必要です。
更地にするためには、建物の解体費用がかかりますが、解体後に買主がすぐに決まらない場合、土地の固定資産税が増加する可能性があります。
また、建物を解体して更地にする前段階として、その土地が何ら問題なく利用可能であるかを確認することが絶対条件となります。
稀に、何かの理由で建築基準法に抵触し新たな建物の建築が許可されない土地が存在します。
つまり、該当の土地については、いかに解体して更地になったとしても、新築の建物を建設することは許されません。
そのため、更地にする前にしっかりと土地が問題なく使用できるかを確かめることがポイントとなります。
例えば再建築不可となるのは、幅員4m以上の道路への接道が2m以上ない土地です。
なお、再建築不可の土地は通常、都市計画区域および準都市計画区域に限られます。
再建築不可の土地に既存の建物がある場合、増築は認められませんが、リフォームして売却するか、更地にして建築不可という条件で売却することが可能です。
しかし、再建築不可の土地は相場に比べて安い価格になる可能性が高いため、注意が必要です。
自治体で土地が再建築不可かどうか確認し、適切に取引を進めることが重要です。
相続した土地を売るには、まず名義変更が必要!手続きのポイントとは?
相続した土地を売却するには、まず名義変更が必要です。
なぜなら、相続は共有状態であるため、名義が被相続人のままだと、第三者に所有者が分からず不動産を売却することができません。
そのため、まず相続登記を済ませて登記簿の所有者名を変更しなければなりません。
相続手続きには、戸籍謄本、除籍謄本、住民票といった書類が必要です。
自分で手続きすることもできますが、時間や手間がかかるため、相続案件を扱う司法書士に依頼することをおすすめします。
依頼する際の手数料は、目安として5~10万円前後です。
また、相続した土地を売却する際には「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」が利用できる場合があります。
この特例は、相続した財産を一定期間内に譲渡した場合に、相続税額の一部を譲渡資産の取得費に加算できるという制度です。
これにより、税金を軽減することができます。
特例を受けるための要件は3つあります。
まず、相続や遺贈により財産を取得していること、次に、その財産を取得した人に相続税が課税されていること、そして最後に、その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していることです。(国税庁ホームページ「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」より)
特例を受けるためには確定申告が必要となりますので、事前に必要な書類を確認しておきましょう。
相続した土地を売却する際には、まず名義変更を済ませ、登記事項証明書の所有者名を変更しておく必要があります。
また、相続財産を譲渡した場合の特例を利用することで税金を軽減することができます。
手続きには時間や手間がかかるため、専門家に相談することをおすすめします。
共有名義の土地を売却する3つの方法がある
土地を複数人で共有している場合、売却をする際にはいくつかの方法があります。
まず、共有者は持分割合を確認する必要があります。
持分割合とは、所有権の割合を示すもので、土地登記事項証明書で確認できます。
法務局で手続きを行えば誰でも取得可能です。
一つ目の方法は、自分が持っている持分の土地のみを売却する方法です。
ただし、持分単位での売却は少ないため、共有者同士の間で売買が行われることが一般的です。
二つ目の方法は、共有している土地を複数に分け、それぞれの持分を売却する方法です。
この場合、分筆という手続きが必要となります。
分筆とは、土地を持分割合に合わせて分けることを指します。
分筆することで単独の名義が複数でき、共有状態ではなくなるため、各自が自分の持分の土地だけを売却することが可能となります。
三つ目の方法は、共有者全員の同意によって土地を売却する方法です。
全員が売却に同意した場合、共有者全員が売主となります。
売却が決定し、契約する際には、全員が同席し、実印の押印が必要です。
売却代金は、持分割合に応じて分配されます。
土地共有の売却には、上記の3つの方法がありますが、どの方法を選ぶかは、共有者同士の協議や意見の一致が必要となります。
売却をする際には、事前に持分割合を確認し、各自の権利義務を理解した上で、円滑に進めていくことが重要です。
農地の売却には許可が必要!手続き方法と注意点
農地を売却する際には、農業委員会の許可が必要です。
まずは、農地の種類を確認しましょう。
一般的に、農地として指定されている場合は、売却に許可を要します。
農地の種類は所在地の自治体や農業委員会に問い合わせるか、農地の登記事項証明書を取得して確認しましょう。
農地を売却するためには、まず農業委員会から許可を取得する必要があります。
農業委員会には、売却の意志を伝え、所定の書類を提出することが必要です。
許可が降りれば、売却を進めることができますが、注意点もあります。
農地を宅地へ転用する場合は、更なる手続きが必要となります。
一般的には、農地を宅地へ変えることは許可されていませんが、特例として宅地への変更許可の取得が可能なケースもあります。
ただし、宅地への変更が認められるかどうかは、農地の種類や所在地の都道府県や市区町村によって異なりますので、確認が必要です。
農地の売却は国の政策の一環であり、許可が必要な場合がほとんどです。
売却する際には、農業委員会への連絡や許可申請などの手続きを正確に行い、法律に則って進めることが大切です。
また、農地を宅地へ変更する場合は、宅地への変更許可の取得が必要となりますので、事前に確認しておきましょう。
賃貸中の土地を売却方法と注意点
現在賃貸中の土地を売却する場合、借地人が立ち退いた後に売却するか、借地したまま売却するかの2つの方法があります。
ただし、借地契約の種類によって留意点が異なってきます。
「定期借地契約」の場合は、契約期限が到来すると借地人が土地を返還するため、立ち退いた後に売却することができます。
一方で、「普通借地契約」の場合は、借地契約の解約には借地人の同意が必要です。
土地所有者側の一方的な理由で解約することは事実上不可能です。
ただし、普通借地契約が設定された土地であっても、そのまま売却することは可能です。
ただし、この場合の成約価格は一般的な土地に比べてかなり低くなる傾向があります。
その理由は、土地を購入しても利用が制限されるためです。
借地料が入るとしても、土地所有者は土地を自由に利用できないため、売買価格が安くなる場合があります。
賃貸中の土地を売却する際には、借地状態の土地の扱いに詳しい不動産会社に相談することをおすすめします。
彼らは借地状態の土地の特性や売却方法についての知識を持ち合わせており、適切なアドバイスや手続きのサポートをしてくれます。
また、借地人との交渉や解約手続きなどの複雑な手続きも代行してくれる場合があります。
土地の売却は大きな取引であり、特に賃貸中の土地の場合は注意が必要です。
借地契約の種類や借地人との関係によって異なる売却方法を選択することができるため、専門家のアドバイスを受けながら無理なく土地を売却するようにしましょう。
土地を損せず高く売るための3つの条件
事前に自分で相場を調べておく
自分の土地の相場価格を正確に知るためにはどうすればいいかご存知ですか? 不動産会社に査定を依頼することも一つの方法ですが、相場に見合った価格なのか判断するためには、事前に自分で相場を調べておくことが重要です。
万が一適正でない価格で査定されてしまっても、相場を把握できていればそれに気付くことができ、価格の理由を質問することもできます。
相場を調べる方法はいくつかありますので、複数の方法で情報を集めることがおすすめです。
まず一つ目は、周辺の物件の価格を調べる方法です。
不動産情報サイトを利用して、住所が近い物件や条件が類似した物件の売り出し価格を参考にしてみましょう。
これにより、自分の土地の相場に近い価格帯を知ることができます。
次に、公的な地価情報を活用する方法もあります。
国土交通省の土地鑑定委員会が公示する標準地の価格や、相続税、固定資産税などの計算に用いられる路線価や固定資産税評価額などは、公的な情報として参考になります。
詳しいデータは国土交通省の「土地総合情報システム」などで確認できます。
さらに、過去の取引データも相場を知るための重要な情報源です。
実際に過去に成立した取引実績の価格の平均値である実勢価格は、売主や買主の状況が反映されています。
国土交通省の「土地総合情報システム」の「不動産取引価格情報検索」を利用すれば、簡単に過去の取引データを調べることができます。
これらの方法を組み合わせて使うことで、より正確な相場価格を把握することができます。
自分の土地を高く売るためには、相場に精通しておくことが必要です。
是非、上記の方法を活用して、自分の土地の相場価格を把握してください。
土地の手入れは重要!不動産会社や購入希望者の印象を良くしよう
土地をきれいに手入れすることは、不動産会社の査定額を高めるだけでなく、購入希望者にも良い印象を与えることができます。
特に更地や空き家は、手入れをしていないと雑草が生えたり、建物が老朽化したり、ごみが捨てられたりする恐れがあります。
このような状態で査定や見学を受けると、不動産会社や購入希望者からの印象が悪くなってしまう可能性があります。
その結果、同じ条件でも査定額が低く見積もられたり、売り出しても買主が見つからなかったり、値下げ交渉をされてしまうことが考えられます。
そのため、できるだけ土地をきれいに手入れしておくことが重要です。
特に遠方にある土地の場合、管理が難しいこともあります。
しかし、放置しておくと土地の状態はますます悪くなってしまいます。
そんなときは、専門の業者に依頼して手入れをしてもらうことをおすすめします。
業者は草刈りや除草剤を使った処理、建物の修繕など、きれいな状態にするための様々な作業を行います。
適切な施設や道具を持っているため、効率よく手入れを行うことができます。
また、業者のプロの目にかかれば、自分では見落としてしまうような細かい箇所も見逃さずに手入れしてもらうことができます。
土地の手入れは、査定や売却活動を進める上で非常に重要です。
手入れが行き届いている土地は、不動産会社や購入希望者からの印象が良くなります。
印象が良い土地は、査定額も高くなり、売却活動もスムーズに進めることができます。
そのため、土地の手入れを怠らず、適切な時期に業者に依頼して手入れをすることをおすすめします。
また、手入れにかかる費用は投資と考えて、将来的な利益を考えることも大切です。
土地売却のための時間配分の重要性
我々が土地を売却しようと考えた場合、即座に売却が完了すると考えるのは誤りです。
なぜなら、土地の売却というのはある一定の時間を必要とするものなのです。
この売却に要する期間はどのくらいなのかと言いますと、考えうる最も一般的なラインとしては、3ヶ月から6ヶ月程度になると想定しておくことが賢明だと言えます。
これはあくまで一例であり、土地の特性や市場状況によって変動することはもちろんあります。
だからと言って、売却を急ぐことによって、価格や条件の面で自分が納得できないレベルにまで妥協してしまうことは、絶対に避けるべきですね。
このような事態を避けるためには、時間的余裕を持った上で売却計画を立てることが必要不可欠です。
具体的には、土地売却のための進行計画を早めに立て、着実にそれに沿って進めていくことで、納得のいく結果を得ることができるのです。
土地売却は一見煩雑に見えるかもしれませんが、時間をしっかりと配分すれば必ずや良い結果を引き出すことができるでしょう。
売却計画のあり方を見極めて、自分自身が納得のいく形で土地を売却できるよう心がけていきましょう。
後悔のない売却を実現するために、時間配分の重要性を理解し、適切な行動をとることが求められます。
土地が売れない原因と解決策
周辺の相場よりも高い
土地を売りたいのになかなか買い手が現れないという場合は、周辺の相場よりも高い価格設定が原因かもしれません。
まずは売り出し価格を見直し、現実的な価格に設定し直しましょう。
相場に合っている価格であれば、買い手も興味を持ちやすくなります。
古家付き土地の家が老朽化し過ぎている
もし土地が古家付きの場合は、家をリフォームすることも考えましょう。
壊れた箇所を修繕し、家の状態を改善することで、買い手がつく場合もあります。
古い家でも、内装や外装をリフォームすることで見た目をよくし、魅力的な物件としてアピールすることができます。
もし土地が都心ではなく、自然豊かな地方や遠隔地などの場合は、空き家バンクへの登録を検討してみましょう。
空き家バンクは、自治体やNPO法人が運営するサイトで、空き家を売りたい人と買いたい人をつなぐ役割を果たしています。
登録することで多くの人に物件が知られる可能性があります。
土地のアクセスが悪すぎる
アクセスが悪い田舎の土地の場合は、売却する代わりに土地の活用方法を考えることも一つの選択肢です。
例えば、農地であれば市民に貸し出して農業体験の場として利用することもあります。
また、建物を建てられるエリアであれば、サービス付き高齢者住宅を建設するなど、土地の特性を活かした新しい使い方を考えることができます。
共通の解決策「買い取り」
最後に、なかなか売れない場合は不動産会社に買い取ってもらう「買取」も考えてみましょう。
ただし、買取の場合は相場よりも安い値段となる可能性がありますので、それを覚悟しておく必要があります。
売却が難しい場合はこのような方法も検討してみると良いでしょう。
売却資金で住宅ローンの残債をカバーできない
ローン返済が残っている土地でも売却は可能ですが、抵当権が付いたままでは第三者に売ることはできません。
ですので、住宅ローンの残債がある場合は、売却時に取引価格で残債を一括返済し、同時に抵当権を抹消する必要があります。
売却資金が残債をカバーできれば問題ありませんが、取引価格が低い場合や自己資金が足りない場合は、追加で自己資金を用意する必要があります。
そのためには、土地がどのくらいの値段で売れるのか、残債は具体的にいくらなのか、自己資金がどれくらい必要なのかなど、資金計画を明確にしておくことが重要です。
不動産会社の「囲い込み」に遭遇してしまう
「囲い込み」という言葉、これは具体的には不動産業界においてよく使用されるもので、その中での売買仲介業務を取り扱う業者の行動を指しています。
売主から不動産の売買に関する仲介を依頼された不動産業者が、他の仲介業者からの質問等を一切受け付けず、自己の業務範囲のみで売買の取引相手を見つけ出すという具体的な行動のことを指します。
なぜ「囲い込み」なのかというと、その業者が売主である方と買主となる方双方の取り引きを、他の仲介業者を一切介入させず、自己の業務範囲だけで完結させようとするからです。
しかし、この「囲い込み」による両手仲介といわれる行動、それ自体は現行の法律では違法行為には該当しないので、「囲い込み」という行為自体を見つけ出すのが難しいという側面があります。
それにもかかわらず、この行為は売主である方も、買主となる方も、どちらにも不利益をもたらす可能性があります。
確かに、自社だけで売買を完結させる業者にとっては効率が良くなるかもしれませんが、依頼者、つまり売主である方にとっては不利益に感じるケースが多いです。
売買に関するスケジュールが予定より遅れてしまうことが多いのです。
また、価格についての交渉もスムーズに進まない可能性もあります。
そして、売主だけでなく、買主となる方にも不利益が出ることもあります。
例えば、物件の内見ができないなど、購入における重要な判断基準を失う可能性があるのです。
さらに、業者が「囲い込み」を行おうとする際、他の業者からの質問等に対しては、「現在、買主と交渉中ですので…」や「内見の準備が整うまでお待ちいただけますか?」などという言葉を使って、自分で買主を探し出すまでの間、外部からの問い合わせを一切受け付けないようにします。